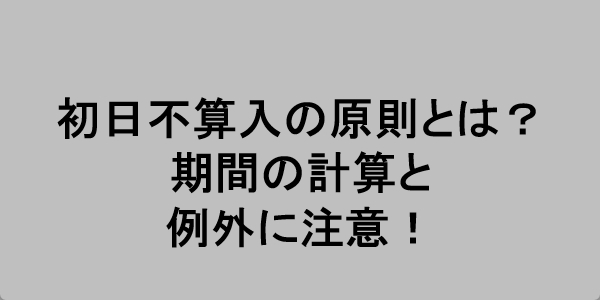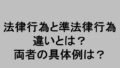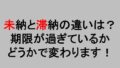法律の世界には、「初日不算入の原則」というものが存在します。
何らかの契約で期限を設定し、起算日が明示されている場合には、その指定に従うのはもちろんのことです。
しかし、起算日が特に定められていない場合や、特定の法律で起算日が決まっているケースを除き、この原則が適用されることが一般的です。
初日不算入とは、文字通り、期間計算の際に最初の日を含めないということです。
ただし、この原則は意外と複雑で、理解するのが難しい場合もあります。
条文を読むだけだと、意味が分かりにくいんですよね。
私自身も、この原則を学び始めた頃は、わりと苦戦したものです。
さらに、初日不算入には例外も存在し、これらの例外についても理解しておくことは大切になります。
そこで、この記事では、初日不算入の原則と例外について、詳しく説明しています。
初日不算入の原則とは?
「初日不算入の原則」とは、期間を日、週、月、または年単位で定める場合に、期間の最初の日をカウントに含めないという法律上の原則です。
この原則は、民法で定められています。
例えば、12月1日に「3日以内に返事します」と伝えた場合、12月1日はカウントに含まれず、3日以内のカウントは12月2日の午前0時から始まります。
その結果、返事の期限は12月4日の終わりになります。
この原則を日常生活に例えると、誕生日の翌日から新しい年齢を数え始めるようなものです。
誕生日自体は新しい年齢にカウントされず、翌日から新しい年齢の1日目となります。
これは、誕生日が完全に終わるまで新しい年齢にならないという考え方に似ています。
初日不算入が適用される場合は?
民法では、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しないと規定されています。
したがって、単位が日以上(日・週・月・年)の場合に、初日を参入しないということになります。
ただ、具体的な計算方法はそれぞれの単位で少し違ってきます。
日の場合
まず、日の場合は、そのまま単純に日で計算します。
例えば、今から8日以内とした場合、現在が12月1日とすると、12月1日を入れずに翌日の12月2日から計算し、12月9日の終わり(午後12時)までとなります。
週の場合
続いて、単位が週の場合は、日に換算して計算します。
1週間は7日間になりますよね。
この7日で数えるということになります。
例えば、今から1週間以内とした場合。
現在が12月1日とすると、12月1日を入れずに翌日の12月2日から計算し、7日後の12月8日の終わりまでとなります。
月の場合
次に、月の場合を説明します。
ここから、さらにややこしくなります。
単位が月のときは、日に換算しません。
暦にしたがって計算することになります。
そのうえで、起算日に応当する日の前日が満了日となります。
初日を入れないのは今までと同じですが、満了日に気を付ける必要があります。
例えば、今から3ヶ月以内とした場合、現在が12月1日とすると、翌日の12月2日から計算し、その応当日は3月2日になります。
そして、その前日の3月1日の午後12時で期間満了となります。
また、月によって期間を定めた場合に、最後の月に応当日がない時は、その月の末日が満了日となります。
例えば、現在が12月31日で、今から2ヶ月以内とした場合。
12月31日の応当日は、2月31日となりますが、暦の上では2月31日は存在しませんよね。
したがって、この場合は、2月28日(閏年の時は29日)が満了日となります。
このように、単位が月の場合、28日の月もあれば、30日や31日の月もあるので、それによって日数は変わってきます。
なので、月単位で期間を設定する場合は、その月の日数によって、期間の長さが異なることを理解しておく必要があります。
年の場合
年が単位のときも、月の場合と同じように暦にしたがって計算します。
この際、起算日の翌日から期間計算が始まります。
例えば、現在が2023年1月1日として、2年間という期間が設定された場合、起算日である2023年1月1日はカウントに含まれず、2023年1月2日から期間の計算が始まります。
その結果、満了日は2025年1月1日の終了時となります。
また、年単位の期間計算では、平年と閏年の違いも考慮する必要があります。
上記の例で言えば、2024年が閏年であるため、その年は366日となります。
このように、閏年が含まれる場合、期間の長さが異なりますね。
初日不算入の例外は?
例外の一つは、民法140条の但し書きに記載されており、期間の最初が午前0時から始まる場合、初日を算入することができます。
例えば、契約書で「12月1日から1年間」と定められている場合、その契約の趣旨が12月1日の0時から1年間を意味する場合、初日である12月1日が期間に含まれます。この場合、満了日は翌年の11月30日となります。
また、法律や契約で特に初日を含むとされている場合も、初日不算入の原則が適用されません。
例えば、「契約の日から起算して7日」という表現がある場合、契約の日自体が期間計算の初日としてカウントされます。
さらに、年齢計算に関する法律では、「年齢は出生の日より起算する」と明示されており、生まれた日を初日に含むことが定められています。
したがって、例えば2023年1月1日に生まれた人は、2040年12月31日の午後12時(つまり2041年1月1日の0時)に成年に達するということになります。
また、特定商取引法では、クーリングオフの期間計算において「書面を受領した日から起算して」とされ、受領日が初日に含まれます。
その他、戸籍法第43条なども、この例外に含まれると考えられます。
戸籍の届け出期間は、届出事由が発生した日から期間を起算することを定めています。
そのため、事由が発生した日が初日になるわけです。
これらの例からわかるように、初日不算入の原則は多くの場合に適用されますが、特定の条件下では例外が認められています。
特に、各種の法律や契約においては、初日不算入の原則に関する具体的な規定と異なる場合があるため、関連する法律を逐一確認し、適切な期間計算を行う必要があります。
契約や法律の文言を正確に理解し、適切に期間を計算することが大切になるというわけです。
まとめ
初日不算入の原則については、まず原則が適用される場合の期間の計算方法を把握するのが重要ですね。
そのうえで、例外となる、期間の最初が午前0時から始まる場合と、各法律の規定に注意する必要があります。
法律や契約の文言を正確に理解し、適切に期間を計算することは、法律の世界での重要なスキルとなります。