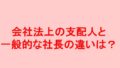日本国憲法は国民の多くの権利を規定していますが、法人は自然人ではないため、これらの権利がどの程度法人にも適用されるかは議論の対象となります。
同じように、外国人の人権もよく問題となるので、セットで理解しておくのがよいでしょう。
この記事では、最高裁の判例と学説に基づき、法人の権利保障の範囲について解説しています。
法人の人権が保障される範囲
まず、法人が現代社会で重要な役割を果たす社会的実体であることを考慮すると、一定の人権を法人にも適用するのが妥当だと考えられます。
この解釈は、通説や判例でも支持されています。
具体的には
- 法人にも保障される人権:経済的自由権全般、精神的自由権の一部、受益権など
- 法人には保障されない人権:自然人固有の権利や、選挙権・被選挙権などの参政権
となります。
以下にそれぞれの人権について、詳しく解説していきます。
自由権
自由権については、主に経済的自由権と精神的自由権に分けられますが、それぞれ認められる範囲が異なります。
経済的自由権
経済的自由権は、その性質上、法人に対して全般的に認められるべきと考えられます。
法人が経済活動を通じて社会に貢献し、経済発展を促進する主体であるため、その人権を保障することは当然と言えるでしょう。
また、経済活動だけでなく、政治、宗教、文化的な活動においても法人は重要な役割を担っています。
これらの分野での法人の活動を通じて、さまざまな社会的・文化的価値が生み出され、公共の福祉が促進されるので、これらの活動に関しても一定の保護が認められます。
例えば、憲法第29条で財産権が保障されているように、法人が所有する財産の自由な使用、収益、処分が認められます。
22条では営業の自由の保障が規定されていますが、これにより、法人は自由に事業を展開することが可能となります。
ただし、現代になって法人の影響力が増大しているため、自然人よりも厳しい規制が認められることがあります。
独占禁止法で市場での独占を防いで、不公正な取引を制限したり、環境規制で廃棄物の管理、資源の持続可能な使用などを義務付けるといった措置などがその例です。
精神的自由権
精神的自由権は、原則として自然人特有の権利とされることが多いです。
ただし、法人にも限定的に適用される場合があります。
21条の結社の自由はもちろんですが、同じ21条の表現の自由の保障は、一般の企業のみならず、特に軽道機関が報道をする場合に重要となります。
また、プライバシーの権利や環境権なども、法人に適用されると考えられます。
しかし、思想や良心の自由は、その性質上、自然人に固有のものとされ、法人には適用されないのが通常です。
法人は合意形成の結果として意思を持つことができますが、個々の法人メンバーの個人的な思想や良心とは区別されるためです。
また、ややっこしいのが、法人が設立目的以外の活動を行った場合です。
特に法人が政治活動を行う際に問題になります。
一般的な学説は、その活動が他の市民の政治的自由を不当に制約する可能性があり、また法人のメンバー間の意見が異なる場合に内部で衝突が生じる可能性があるため、個人とは異なる特別の規制が必要であるとする見解が多いです。
この点に関して、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決(最大判昭45・6.24)の有名な判例があります。
当時の八幡製鉄株式会社の取締役が会社名義で自民党に政治献金を行いましたが、これに対し、株主が会社が被った損害を会社に支払うよう求めた事件です。
最高裁判所は、営利法人である八幡製鉄株式会社にも政治献金の自由が憲法上保障されており、自然人たる国民による寄附と別異に取り扱うべき憲法上の要請はないと判断しました。
ただし、この判例に関しては、法人の政治献金が個人の政治的自由権と同様に扱われるべきかについて議論があります。
学説からの批判も多く、法人の影響力と資源が個人よりもはるかに大きいため、これによって政治が過度に影響を受ける可能性があると指摘されています。
また、全ての法人に政治活動の自由が全面的に認められているわけではなく、南九州税理士会政治献金事件(最判平45・6.24)では、南九州税理士会が行った政治献金について、最高裁は、税理士会の目的の範囲外の行為であって許されないとしました。
この判例では、政治団体に金員の寄付をするかどうかは会員各自の個人的な判断によって自主的に決定すべき事柄であるとした上で、税理士会が強制加入団体であり、実質的に脱退の自由がないという点を考慮しています。
逆に、群馬司法書士会震災支援寄付事件(最判平14・4.25)では、被災した兵庫県司法書士会に三千万円の文援金を寄付をすることを決定した事案で、他の司法書士会に協力や援助をすることは活動範囲に含まれるとし、支援金の寄付は権利能力の範囲内で許されると判示しています。
このように、法人の政治的活動は、その活動の目的や法人の種類と性質、さらにはその活動が持つ社会的影響や法人内部の意見の一致程度などに基づいて、ケースバイケースで判断されるということです。
受益権
受益権とは、国や公共機関からの特定のサービスや恩恵を受ける権利を意味します。
受益権も基本的人権の一つで、国務請求権と呼ばれるともあります。
具体的には
- 請願権(第16条)
- 国家賠償請求権(第17条)
- 裁判を受ける権利(第32条)
- 刑事補償請求権(第40条)
の4つがあげられます。
これらの権利はすべて、国または公共の機関に対して正当なサービスや補償を求めるもので、特に法人であるためにこれを否定する理由はないわけです。
たとえば、法人が不当な行政手続きによって損害を受けた場合には、国家賠償請求権を行使して損害賠償を求めることができます。
参政権
参政権のうち、特に選挙における投票権と被選挙権は、基本的に自然人専有の権利とされています。
法人は個々の人格ではなく、多くの個人の意思が集合した結果として成立するため、一貫した政治的意見を持つとは限らないことが、その理由です。
さらに、法人に参政権を与えることは構成員が個人として既に持っている権利に加えて、法人としての影響力も行使することになり、投票の平等性が損なわれる可能性があります。
また、法人は商業的利益を追求する目的で設立されることが多いため、政治的に中立であるべき立場からも参政権を持つべきではなく、政治的決定が商業利益に左右されるのを避けるためです。
これらの理由により、参政権は個人の基本的な人権として自然人にのみ認められるというわけです。
自然人固有の権利
自然人固有の権利とされるものは、法人には認められません。
例えば
- 個人の尊厳(第13条)
- 身体の自由(第18条)
- 生存権(第25条)
などです。
これらの権利は、自然人に固有のものとされており、法人などの集合体には直接適用されることはありません。
個人の尊厳や生命や身体の自由というものは、個々の人間特有のものであるためです。
常識的に考えても、これらを法人に適用することは理論上不可能ですよね。
法人は生物学的な存在ではなく、法的に認められた存在です。
自然人に適用される身体的または精神的な健康に関する権利を、法人に保障するというのは無理があるということです。
まとめ
人権は基本的に個人の権利ですが、権利の性質に応じて法人にも適用されるものがあります。
判例と学説を見ると、経済的自由権全般や精神的自由権の一部、受益権などが法人に保障されることが一般的です。
しかし、自然人固有の権利や参政権などは法人には認められていません。
法人の人権を把握するには、それぞれの権利の性質をよく理解したうえで、どのように適用されるかを具体的に考察することが大切になります。